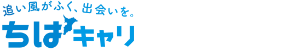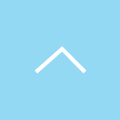「組織づくり」と「人材採用」が企業成長のための最重要テーマ
会社に行くのが楽しい!と思える風土を醸成し、新たな人財を採り、育てる

合資会社寒菊銘醸
明治16年に創業者が当地の伏流水と豊富な米を用いてすっきりとした辛口の日本酒の醸造を開始して以来130年、長く愛される伝統の味を守りつつ、日本酒とクラフトビールの製造・販売と、時代に合わせたお酒造り・事業を展開し続けています。
本社所在地:千葉県山武市松尾町武野里11
設立:昭和5年10月25日
従業員数:23名
代表者:代表社員 佐瀬 建一
会社HP:https://kankiku.com/
|
導入の理由 |
・受注量が大幅に増える中、人員増強の必要性を感じていた |
|---|---|
| 導入前の課題 |
・ハローワークを中心とした公募での応募者では、当社の求める人材像とのミスマッチが多かった |
| 導入後の成果 |
・出荷部門や製造部門、クラフトビールバーの店舗スタッフなど計4名の採用ができた |
出荷部門、製造部門、新規事業のスタッフなど4名の採用に成功

合資会社寒菊銘醸 代表社員 佐瀬 建一 氏
当社は創業130年の歴史を持つ酒造メーカーです。市場の縮小やコロナ禍という逆境の中で、10年ほど前に私が経営の全責任を負うことになったことを機に、大きな改革に着手しました。
歴史や伝統を守るだけでは生き残れないと判断し、組織や労働環境を一から見直し、大胆な改革を行ったのです。その時の取組みが、現在の採用力や組織力、社員の成長につながっていると感じています。企業成長のために特に重要なテーマは、「人材採用」と「組織づくり」だと考えています。
経営環境の変化に応じて求める人材像も変化
酒造業界は市場の縮小が加速し、変化のスピードも一段と速まっています。これまでは10年単位で事業を考えればよかったものが、今や5年、あるいは1年単位で変化に対応しなければなりません。そのような急激な変化の中で、求める人材像に対する当社の考え方も大きく変わりました。
従来の「現状維持型」ではなく、変化を恐れず、経営陣の号令に共感しながらも主体的に動き、一緒に変化を楽しみ、乗り越えていけるフレキシブルな人材が必要だと考えるようになったのです。
この考えに基づき、新しい価値観を持つ若手社員を積極的に採用・登用し、大胆な組織改革を行うことを決断。高齢化が進んでいた社員の若返りを図るため、次世代、特に子育て世代が働きやすい環境づくりをすると決め、既存の枠組みにとらわれず、一から改革を進めていったのです。
まず、酒造業界では冬季の生産が多い中、年間を通じた生産体制への切り替えを実施し、従来の季節労働から脱却しました。これにより、社員が年間を通じて計画的に働き、自由に休みを取れる環境を整備しました。現在、当社では年間休日と有給休暇を含め125日程度を取得できる上、定時退社が基本です。毎日17時以降はほとんど残業がないという働きやすい環境を整えています。
特に子育て中の女性パートスタッフが働きやすい環境を構築するため、勤務時間を9時~15時に設定。気兼ねなく子供を保育園などへ迎えに行けるようにしました。また、正社員とパートなど、雇用形態の違いに関係なく、公平な給与体系や待遇を導入し、パートでもしっかり有給取得ができる環境を整えました。いわゆる同一労働同一賃金の走りです。
これにより、自然と優秀な人材が集まるようになっただけでなく、現場が活気づき、仕事に対する取り組み方もどんどん前向きに変わっていきました。特に指示がなくても、社員やパートスタッフが自ら目標を設定し、業務改善に取り組んでくれるようになったのです。
例えば、段ボール梱包の標準目標を1時間に100箱としていたところ、「120箱作ることを目指そう」と自主的に業務改善に取り組むといった姿勢が現場から自然に出るようになりました。こうした自主性や向上心が現場に浸透したことで、生産性が向上しただけでなく、事故の発生もほとんどなくなり、安心して仕事を任せることができています。
このような活気ある状態を維持するために、特に私が気を遣っているのは、社員が働きやすく、意欲を持てる環境にするためのコミュニケーションの場を創出することです。月に一度のランチ会や年数回の社内イベントを実施しています。先日も、自社の店舗を貸し切りにして、懇親会を行ったところです。
スタッフが自主性をもってモチベーション高く働いていけるようにするには、「会社に行くのが楽しい」と思ってもらえることが大事だと私は思っています。皆が喜ぶコミュニケーションの場を作ることによって、「会社に行くのが楽しい」という雰囲気ができ、チーム寒菊としての一体感を醸成しています。
アナログなやり方ではありますが、お互いに気兼ねなくモノが言える雰囲気ができていますし、現場の士気が高まり、チーム全体での業務効率の向上につながっています。
地元人材の採用強化を目的に「ちばキャリ」の利用を決断
そんな状況で、採用を強化するためにネットで調べて問い合わせたのが「ちばキャリ」さんでした。
私は、そもそも採用活動にコストをかけすぎることに懐疑的で、大手求人媒体を利用する気はありませんでした。中小企業が採用活動に数十万円もかけるのは合理的ではないと思っていましたし、求人にそんなお金をかけるくらいなら、その資金を社員に還元した方が良いとさえ考えていて、これまでは主にハローワークなどを活用して採用を行っていました。
それでも、「ちばキャリ」を利用したいと思ったのは、地元人材の比率を増やしたいという思いがあったからです。人が足りない状況ではありましたが、少しずつ人材の採用はできていました。認知度が高まるにつれ、ブランドや事業内容に共感した人材が幅広い地域から集まるようになっていたのです。
これは非常にありがたいことでしたが、反面、遠方からの応募・採用が増えることで、住宅手当や交通費補助など、人件費に関連する費用がかさみ、企業としての負担が増加していました。さらに、地域に根ざした企業として、地元の人材を育成し、地域全体の発展に貢献するという理念を大切にしたいという思いも強くありました。こうした背景から、地域特化型の求人媒体である「ちばキャリ」を使ってみようと思ったのです。
実際に「ちばキャリ」を利用して感じたのは、応募者の質がとても高いという点です。これまでの公募では、単純に働き口を求めているだけで、当社の事業や自分の将来像への関心は低いという方が多かったのですが、「ちばキャリ」経由で応募してくる方は、「千葉で働きたい」という明確な意志を持ち、将来像をしっかり描いている意欲的な方が多いと感じました。
結果として、出荷部門や製造部門、新規事業であるクラフトビールバーの店舗スタッフなどで計4名の採用ができました。彼らは当社の考え方や価値観、事業ステージとしっかりマッチし、即戦力として活躍しています。
採用が成功したのは、当社が取り組んできた組織変革や労働環境の改革など、前向きな変化を求める躍動感や社員の一体感が、求人原稿を通じて求職者に伝わった成果だと感じています。また、早い段階から自社HPに採用情報ページを設け、当社の考え方や価値観を発信してきたことも、成功要因の一つだと思います。
採用では、仕事の質を左右する気配り力を重視
採用時に重視しているのは、日常生活での気配りや細やかな観察力です。面接では、容姿や身だしなみ、書類の細部からその姿勢を見ています。こうした姿勢は、仕事において品質管理や改善提案に繋がる重要な要素だと考えています。
例えば、製造部門のパートスタッフの一人が、ラベルのわずかな印刷のずれに気付き、すぐに担当者に改善を提案したことがありました。印刷ミスは商品そのものの品質だけでなく、ブランドの信頼性にも影響します。その気づきによって問題を未然に防ぐことができ、結果的に生産性の向上にも繋がりました。
こうした細やかな気づきや改善提案ができるか否かは、日常生活の中でどれだけ注意深く物事を見ることができているか、気を遣えているかに左右されるものです。仕事はチームで進めるものですが、一人ひとりのこうした姿勢が、最終的に全体の品質を高めていくと考えています。
おかげさまで、当社は目標としていた人員確保ができました。新たに採用した人財を活かし、今後も労働環境の整備や経営体制の強化を続けながら、さらなる成長を目指していきます。
時代の変化に柔軟に対応しながら、次の成長ステージに進むときに、再び「ちばキャリ」さんを利用させてもらいたいと考えています。
RELATION
関連記事
CONTACT
まだ採用成功に繋がっていない千葉の企業様、
ぜひ「ちばキャリ」にご相談ください。
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
お電話でのお問い合わせはこちら
平日 10:00~18:00